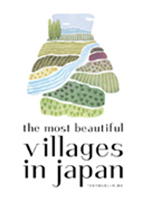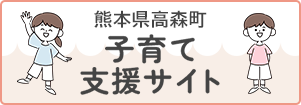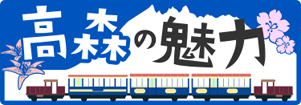本文
個人住民税(町県民税)
個人住民税
毎年1月1日時点で住所がある市町村で課税され、均等割と所得割の合計額が個人住民税となります。
均等割とは前年の所得の合計が条例で定めた金額(扶養親族なしの場合、合計所得金額38万円)を超えた場合に課税されます。※
所得割とは前年度の総所得金額等が条例で定めた金額(扶養親族なしの場合、45万円)を超えた場合に課税されます。※
※扶養人数により増額する場合があります。
個人住民税の非課税になる方
- 障害者、未成年、寡婦(寡夫)の方で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
住民税の徴収方法
(1)給与からの特別徴収
事業所等で給与収入がある場合、会社が給与収入から個人住民税を天引きし、本人に代わり事業所等が納付する方法です。
徴収される期間は6月から翌年5月までの12回になります。
給与での特別徴収を希望される場合、事業所等からの届出が必要のため、勤務先へご相談ください。
特別徴収を行っている人が会社を退職された場合、未徴収分の住民税は、一括徴収もしくは徴収方法が普通徴収(本人納付)に切り替わります。
(2)公的年金からの特別徴収(年金特徴)
65歳以上で年金収入がある場合、年金から個人住民税が天引きされ、本人に代わり年金支払者が納付する方法です。
徴収される時期は年金支給付月の6回となります。
新しく年金特徴になる場合、年税額の半分を6月・8月で普通徴収(本人納付)、残り半分を10月・12月・翌年2月に年金特徴でお支払いになります。
なお、年金特別徴収は、次の1から5のすべてに該当する方が対象となります。
- 前年中に公的年金等の支払いを受けていること。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること。
- 当該年度の4月1日現在において、65歳以上であること。
- 介護保険料が、年金から天引きされていること。
- 個人住民税の納税義務があること。
(3)普通徴収
自営業や農業等の事業所得者の住民税や、特別徴収の対象でない方の個人住民税について、納付書または口座振替にて納める方法です。
納期は6・8・10・12月の4回となります。
もし、12月以降に修正申告等で個人住民税の追加徴収が発生した場合、一括納付になります。また、前年度の修正申告についても同様に一括納付となります。
町民税の申告
所得税と同様、2月16日から3月15日までに申告してください。期日がせまると窓口が混雑しますのでご注意ください。
なお、給与所得者で年末調整を行われた方や、税務署に確定申告を提出した方は申告の必要はありません。
申告書は町県民税や国民健康保険税の計算資料としてばかりでなく各種税証明の発行にも大切な書類です。申告を行わないと、税証明が発行されない、国民健康保険税の軽減が受けられないことがあります。必ず、申告期限までに申告しましょう。